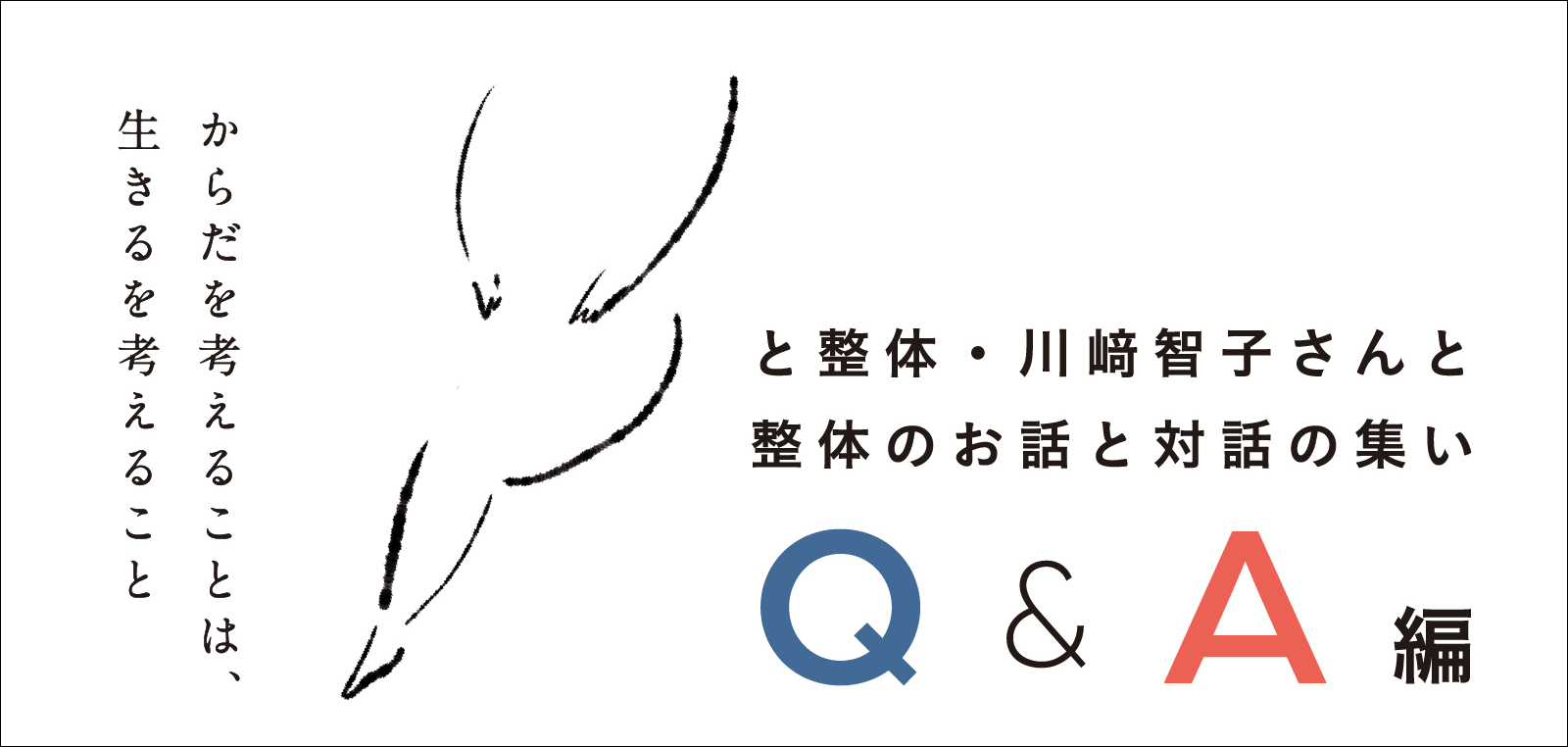川原真由美さんインタビュー その2
「感じる気持ち」が絵に表れてると
おもしろいなと思う
そういう絵を描きだしてから、人にもいいねって言われるようになったんです。それからは、気が楽になった。いままでは、いつまでたってもどんなものを描くのか見えなかったのに、自分に対してそれがはっきりしてきて。うまく描けるかどうか以前に、自分が表現したものがしっかり見えてきたとき安心できたっていうのが実感としてあったんですね。
だから、子どもと一緒に描くときも、ペンで描くようにしています。とくにちょっと大きくなった子どもって、違うって思った線を消そうとするんですよ。描き直そうとしたり、新しい紙に替えようとしたりするけど、そのまま描きつづけてもらうと、すごくいい絵が描ける。違うと思った線をいつまでも認めようとしないと、何回やってもうまくいかず、しまいにはその絵はできあがらない。それを、間違えたと思っても、なかったことにしないで、自分でなんとかしながら続けていく。そうすると、絵ってできあがっていくんです。そうやって描けたとき、その子、すごく自信がつくんですよ。

仕事のときも、時間がないときとか、間違えられないとか、難しいとか、そんなときは、鉛筆でなんとなくアウトラインを下描きすることがあります。そうするとふつうに上手に描けて、おもしろくない絵ができあがっちゃうことがあるんですよ。下描きで1回引いた線って覚えてしまっているから。最初に描く線って、けっこういいんですよね。その人が出てしまうというか。でもそれをよしと認めるのは、難しい。
でも、たとえば実物はこっちが大きくてあっちが小さいのに、描いた絵はあっちのほうががやけに大きく細かく描いてあって、こっちが適当に描いてあったとしたら、それはその人の視点がよく表れているってことだから、おもしろい。その人の目線で、その人の心で見たままが無意識に出ちゃってる状態。つまり、すごいスケッチをしてるってことなんですよ。それを、形をとろうとすることで、すべて殺してしまう。無意識にある読み取り能力を。
視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感ってあるじゃないですか。それ以外にもうひとつあるのが、その「感じる気持ち」だと思うんです。それが絵に表れていると、おもしろいなと思う。
描きたいものを自分の目線で見つけると
絵って描けるんだ
──グラフィックデザイナーだった川原さんがどうしてイラストを描くようになっていったのか、経緯を教えてくださいますか。

最近だったらパソコンがあるから、写真とかを取りこんでラフをつくったりするんでしょうけれど、当時は手作業でした。大きな仕事ではカンプライターと呼ばれる専門の人に描いてもらうこともあるけれど、ふつうはサラサラッと描いた線で、口頭で補足していたんです。線だけだから、具体的には見えないことをプレゼン相手にイメージさせるっていうんでしょうか。本当はそのほうがうまくいくんです。カンプを写真などの具体的なイメージでつくっちゃうと、実際できてきたときに、これでは話が違うなんてことになったりする。カンプがそのまま完成イメージになって刷りこまれてしまうから、そこで相手が止まっちゃうし、自分も止まっちゃう。イメージを限定しすぎない線で描いてたほうが、いくらでも広げられるんですよね。
そんな流れで、私が描いたダミーを見たクライアントが、本番もこのイラストを使えばいいんじゃないの、と。私のイラストの仕事は、たぶんそうやって始まっていったんです。
初めて自由な題材で描いたのは、社内でつくるカレンダーでした。デザイナーが毎年もちまわりで担当するんですが、当時、会社があった丸の内をスケッチしようと思って、丸の内1丁目から5丁目までをスケッチしてまわったんです。社内の人が話しあってる風景とか、会社に清掃に来てくれるおばさんとか、皇居のお堀にいる亀とか、東京駅の靴磨き屋さんとか、道路工事の人とか。
そのときに、これを描きなさいって誰かに言われるんじゃなくて、自分で描きたいものを自分の目線で見つけて描くと、絵って描けるものなんだなって思いました。あと、ペンでいきなり描いてできあがっちゃうのが嬉しかった。

──でも、仕事以外で、自分の楽しみで絵を描くことって…。
そう、さっきも言ったように、あんまりないんです。旅行に行ったときに日記代わりに描くことはあります。私のなかではスケッチというより、メモみたいな感じ。だからどっちかというと、文字を書くのと同じような感覚ですね。わざわざなにかを描くことはあんまりないです。
私はここにいる。
やることがある、できることがあるって
思えるような、自信になる

──描くのが楽しくてしょうがないタイプではない川原さんは、喜びとかモチベーションとか、絵を描くことに対してどこに自分の気持ちがあるんでしょう?
描く前は苦しいんだけど、すごく楽しい瞬間が必ずあるんですよね。それは、ほかでは味わったことがない感覚で、なんかちょっと、どこかの世界に行っちゃったような気分になってしまう瞬間なんです。もしかして、歌手がステージに立つのが怖いのに、立った瞬間になにものにも代え難い気持ちになるみたいな、そういうものなのかもしれない。たしかにそういう瞬間があって、それはたぶんほかのことでは体験できないから、また味わいたいと思ってるのかもしれない。
──それは、デザインの作業のときにはないですか? 絵のときだけ?
デザインでもあるけど、絵のときはもっと強い。デザインは逆に、絵ほど苦しくないんです。整理してまとめていくと、向かう先はデザインが示してくれていて、私はそれを追っていくだけの作業で、絵ほどは煮つまることもない。逆に楽しくて、着手するとやめられなくなる時間のほうが多いんです。絵は、よし、やらなきゃ!と思って、あー、もう駄目だ、逃げたいと思って、違う用事を見つけてやりすごす、みたいな時間が多い。
──(笑)宿題みたい。
そうそう。でもある瞬間にパッとそういう方向になって、あ!って急に見えてきて、終わる。なんなんでしょうね。
──そうですよねえ。それがないと、全部が全部、苦しいだけでは……。
(笑)たしかに。そういうことはないかもしれない。いま言われて考えてみて、初めて気がつきました。なんでやってんだろう?って(笑)。で、やっぱり、その感覚を味わうと、自分の存在が確認できたような気がして初めて落ち着くんですよ。ちょっと自信になるっていうか。絵の出来というよりは、どっちかというと、制作中にその気分を味わっているとき、私はここにいる、みたいな。やることがある、できることがあるって思えるような、自信になる。
──でも仕事って、そういうものかもしれないですね。川原さんが感じるような瞬間を、それぞれの人が、それぞれの仕事で感じて、これでいいんだって安心できるような。
そういうものがまったくなくなっちゃうと、不安定になるっていうか。絵じゃないんじゃないかって、いまでもそういう思いもあります。描くことがけっこうしんどいときがあるので、ほかの人は本当にここまで苦しいのかなって。まあ、楽しいばかりではもちろんないとは思うんだけど。でも、もともと絵を描くのが好きで始めたわけではないから、もしかして違うことがあるんじゃないかっていつも思ってて。だけどいまのところ、その瞬間を味わう感覚っていうのは絵を描いてるとき以外で経験したことはないから、いまはそれがないと、なにもなくなっちゃう気がして。
だから、苦しいんだけど、描いてない期間が長かったりすると、足元がぐらつくような気分になります。なにか欠けてるような、自信がなくなっていくような。

- page 1:川原真由美さんインタビュー その1
- page 2:川原真由美さんインタビュー その2
- page 3:川原真由美さんインタビュー その3

イラストレーターでありグラフィックデザイナーでもある川原真由美さんによる、初の原画展を開催。高山なおみさんの著作や『暮しの手帖』『クウネル』などで、きっとみなさんも見たことのあるイラストを、たくさん展示します。