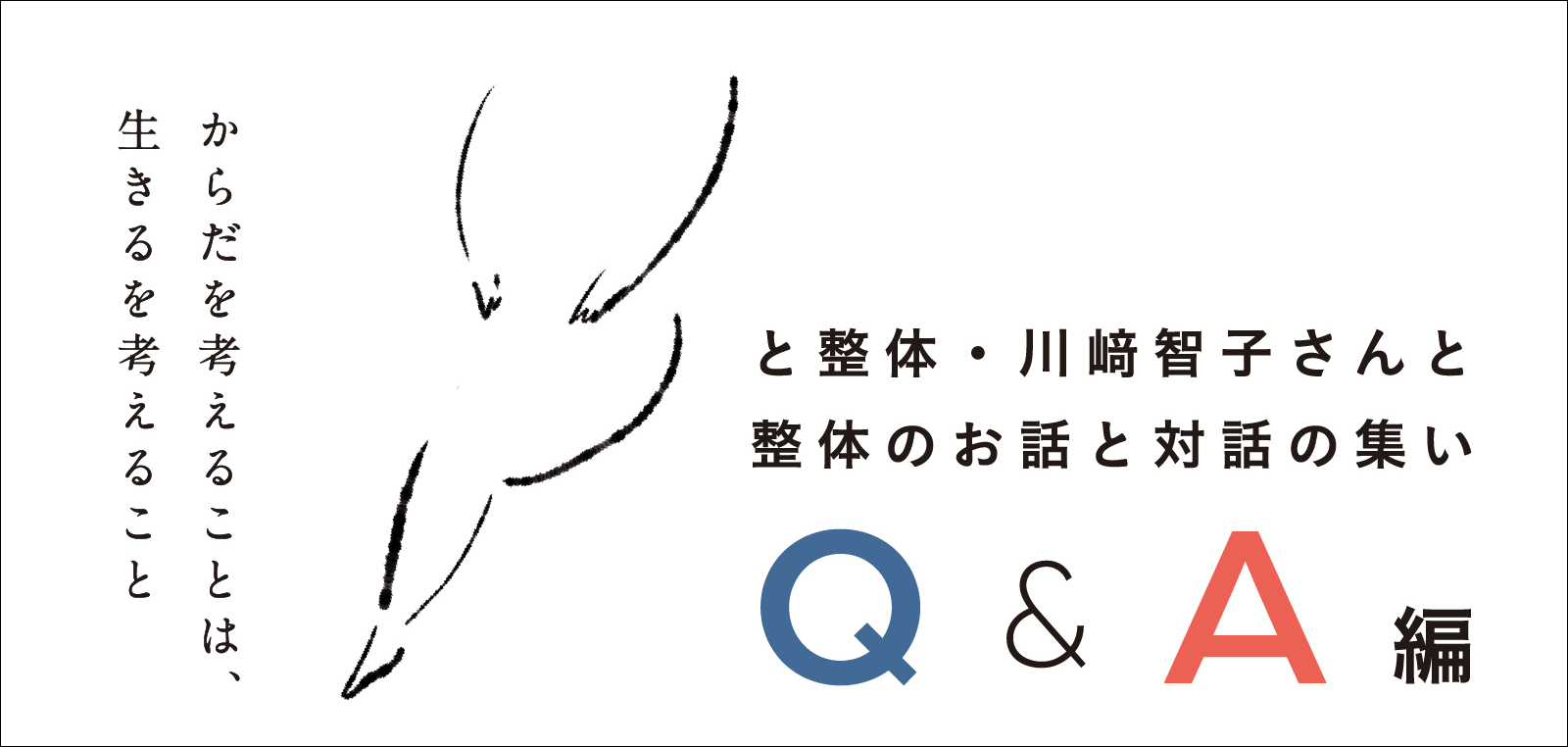今のわたしができるまで第四回
『Daja』 ディレクター 板倉直子さん 〈前編〉
なにもなかったからこそ
自分の世界を大事にできた
充実した仕事をしているあの人も、輝く雰囲気をまとっているあの人も、ゼロから突然、いまいる場所に立っているわけではありません。
誰もがみんな、ときに迷いながら歩き続けて今のところにいる。
この連載では、私たち“くらすこと”がすてきだと思う方々に、これまでの道、今、そしてこれからのことについて、お話を伺っていきます。
構成・文:神武春菜
写真:穴見春樹
第四回にご登場いただくのは、島根県松江市にあるセレクトショップ「Daja」のディレクター板倉直子さんです。〈トラディショナルでスタンダードな服〉をコンセプトに上質なアイテムをおすすめするほか、“くらすこと”で取り扱いがスタートしたブラント「HAND ROOM WOMENS」のディレクションも手がけています。
「『Daja』で働いて今年で34年になりますが、私もまだまだ未完成です。でも、この記事を読んでくださった方にとって、私の経験が、一歩踏み出すきっかけになったら嬉しいです」
板倉さんはそう言って、“今のわたし”につながる糸を、丁寧にたどってくださいました。

ものがなかったということにさえ
気がついていなかった
板倉さんが歩んできた道のりは、「ない」ことの連続だった。子どもの頃は、ものや情報が少なかったし、高校生の時には、父親から「大学に行かせるお金はない」と言われた。成人しても、将来の夢なんてなかったし、人生を突き進む自信もなかった。
「でも、例えば、奥出雲で過ごした子ども時代は、ものや情報がないからこそ、自然と物事を工夫して楽しむクセがつきましたし、20代の頃は、自信がないからこそ、自分の可能性を試してみようと行動して、いろんな景色を見ることができた。結果的に、今、お店をやっていて、とっても役立っていることが多いんですよ」
穏やかな笑顔で、そう振り返る板倉さん。
特に、高校を卒業するまで暮らした奥出雲の環境は、自分の世界を自然と大事にすることができたと慈しむ。
□ □
板倉さんが生まれ育った島根県仁多郡奥出雲町は、「Daja」がある松江の街から、車で1時間ほど南下した、文字通り、出雲地方の奥地に位置する町。広大な棚田が広がる緑深き里山は、同じ島根でも、空気の匂いも、遠くまで澄んだ景色も全く違うそうだ。

「水の都」といわれる松江市。市街地の中心を流れる大橋川からは、西に宍道湖、東に中海が広がる。
小学生の頃は、少女まんが雑誌『なかよし』や『りぼん』が大好きだった。三姉妹の真ん中。新しい号が発売されると、少ないお小遣いをみんなで出し合って1冊だけ買い、姉が読み終わるのをいまか今かと待った。
いざ自分の番になると読み終わるのが惜しくて、一番好きなまんがのページは、ノートに枠線を引いて描き写しながら、じっくりじっくり読み進めていたという。
「当然、付録も1つしかない。それが両面刷りのポスターだったりすると、姉と妹と、どっちを表にして貼るかもめるわけですよ(笑)。結局、両面が見えるように天井から吊るして、ゆらゆら揺れるポスターの好きな絵柄の方を眺めたり……。
思い出すと笑っちゃうような思い出ばかりなんですが、当時は、あるものの中でいかに楽しむかということに常に全力。ものや情報がないということにさえ気がついていなかった」

「推理小説家の横溝正史シリーズを読んで、一人でハラハラドキドキしたり、着せ替え人形の服が足りなければ自分で作ったり、一人遊びが好きでした」
夢は見たい。
でも、夢を見ることさえできなかった
中学生になった板倉さんは、創刊したばかりのファッション雑誌『Olive』に夢中になった。
いちばん楽しみにしていたのがサブカルチャーのページ。フランスの女子学生をさす「リセエンヌ」の暮らし方や、フランスの上流階級のシックな暮らしを意味する「B.C.B.G(ボンシック・ボンジャンル)」のライフスタイル、映画や音楽、古着カルチャーなど、想像すらしなかった世界が自分の中に初めて入ってきて、胸が躍った。

今もさまざまな本や雑誌を読むのが大好きな板倉さん。洋服のデザインや、着こなし方のインスピレーションをもらうことも多いそうだ。
「学校でも、『Olive』好きの友達には、おはようじゃなくて『Olive読んだ?』が朝のあいさつでした。古着ショップやレコード店がひしめく大阪のアメリカ村が私にとって聖地になりつつあって、高校を卒業したら大阪で働きたいと思うようになりました」
都会に憧れるようになった理由はもう一つあった。
米農家と島根和牛の繁殖を家業としていた両親は、家計のために兼業も抱え、365日、休みなく働いていた。
母親は、毎朝5時には起きて畑や田んぼの仕事を終え、一家のお弁当を作ってから兼業先へ。夕方に帰宅し、その足でまた田んぼ作業をしてから、夕飯を作っていたという。
「体力的にも、精神的にも辛そうでした。父が作る『仁多米(島根県仁多郡奥出雲町で作られているコシヒカリ)』は、とても美味しくて誇りでもあったけれど、三姉妹ともとても家業を継ぐ覚悟が出来なかった。
飼育していた牛は家族のようにかわいがっていて、食べることはありませんでしたし、連れていかれる時は『ドナドナ』の歌の気分でしたよ…(涙)。
でも、友だちと電話をしていたら、『モ〜』って牛の鳴き声が入ってきたり、家の敷地から牛糞の匂いがしたり……。多感な少女期の私にとってはそういうことも本当に嫌で、都会にしか憧れが持てなかった。経済的にも『高校までで精一杯』と言われていたので、じゃあ、もう大阪に行って働くしかないなって」

夢は見たい。でも、目の前の現実を見ると夢を見ることはできない。
大学に行って、もっと勉強したかった。そこから自分の夢を見つけて、追いかけてみたかった。
そんな劣等感を抱えながら、社会人のスタートを切ったという。
アメリカ村で過ごした青春時代は、
私の宝物
婦人服を扱う小売店に就職し、無事に大阪での生活が始まった。ところが、1年もたたないうちに退職した。
「配属先だった心斎橋の店舗は、私の中で聖地だったアメリカ村と、目と鼻の先だったんです。〈私が働きたいのは、本当はここ……〉という気持ちが大きくなって、アメリカ村の中にある古着屋に転職しました」
この頃は、田舎で抱えていた葛藤を解き放つように、強い憧れだけをひたすら追いかけていたという。
勤めたお店は、ヴィンテージのリーバイスや昔のロレックスなども取り扱う古着屋。店内には大好きなイギリスのロック音楽が流れていた。
「自分より10歳も20歳も年上のお客さんも多かったんですが、店内に置いてある洋服の価値を詳しく教えてくれたり、おすすめの音楽をカセットテープに録音してわたしてくれたり、お店にいるだけで自分の好きな世界がどんどん広がりました。
仕事が終わると、アメ村の友人たちと喫茶店でチャイを飲みながら音楽の話に花を咲かせて。毎日が、死ぬほど楽しかった」
当時のことを話す板倉さんの表情から、どんなに楽しい日々だったかが伝わってくる。

「でも……」と、板倉さんは一呼吸おいた。
「楽しいけど、どこかで、ここから卒業しないと、って思っていたんですよね」
古着屋の給料だけでは生活が出来ず、出勤前に喫茶店でモーニングのアルバイトもしていたが、菓子パン一つ買うのも迷うくらいお金がなかった。
好きなこととはいえ、経済的にも体力的にも持たない。
資格もないし、仕事の実績があるわけでもない。
「このまま、大阪で根無し草のようになっていくんじゃないかって、すごくこわかった」
これからどう働いて、どう暮らしていけばいいのか。
板倉さんは、島根へ戻ることにした。

その日は必ず来るから。
心の片隅で“その日”を意識して生きる
その頃の板倉さんは、まだ20代前半である。
お金も、自信もなくても、好きな世界に身を置いて、このまま突き進もうという選択肢はなかったのか。
そう尋ねると、小学生の時に、担任の先生が言った言葉を教えてくれた。
「朝の会の時だったかな。先生が、『その日は必ず来る』って言ったんですよ。
“その日”というのは、例えば〈成人する日〉〈働き始める日〉〈仕事を辞める日〉〈還暦を迎える日〉〈両親が旅立つ日〉〈自分がこの世を去る日〉――どこかでまだまだその日は来ないと思っているけど、必ず来ますからねって。
のほほんと聞いてたんですけどね、すごく心に突き刺さったんです。その時その時をやり過ごすように生きていては、なんの準備もないまま“その日”が来てしまう。
悔いがないように生き切るために、何歳までにどうしたいのか。人生の時間というものをどこかで計算するようになったんだと思います」
その言葉は、今も人生のさまざまなシーンで思い出すそうだ。
「心の隅で、“その日”を迎える準備をしていると、いざというときの自分の支えになると感じたことが何度もあって。だから、楽しい時も、つらい時も、あえて立ち止まって、いま何をすべきか、冷静に考えるようにしています」
□ □
姉と妹が住んでいた松江を拠点に就職活動を始めた板倉さん。安定した仕事に就くことが第一条件。夢を追おうなんて、まったく考えていなかったという。
そんな時、友人に頼まれて一時的にアルバイトに入ったのが「Daja」だった。「Daja」は、当時のオーナーが島根県益田市に1号店をオープンしたお店で、松江にも店舗を構えたいとスタッフを探していたのだ。
「次のスタッフが見つかったらすぐに辞めるつもりでしたから、志もなにもありませんでした。まさか、それからずっと勤めることになるなんて、思ってもいなかった」
そう振り返る板倉さんが、「Daja」との出会いを機にどう変化していったのか。
後半に続きます。
お話を聞くひと

板倉直子さん
「Daja」ディレクター
1967年生まれ。島根県松江市にあるセレクトショップ「Daja」ディレクター。ファッションブランド「HAND ROOM WOMENS」のディレクションも手がける。著書に「大人のための かしこい衣服計画」「頑張らないおしゃれ」「明日、ちょっといい私に出会えたら」(いずれも主婦と生活社)、別冊天然生活「大人の悩みこたえるおしゃれ」(扶桑社)がある。
 特集:
特集:
HAND ROOM WOMENS 板倉直子さん直伝
おしゃれのセオリー 1,2,3 vol.1
シルエットや色使い、小物の合わせ方…板倉さんに学ぶ「大人のおしゃれ」の方程式を公開中。