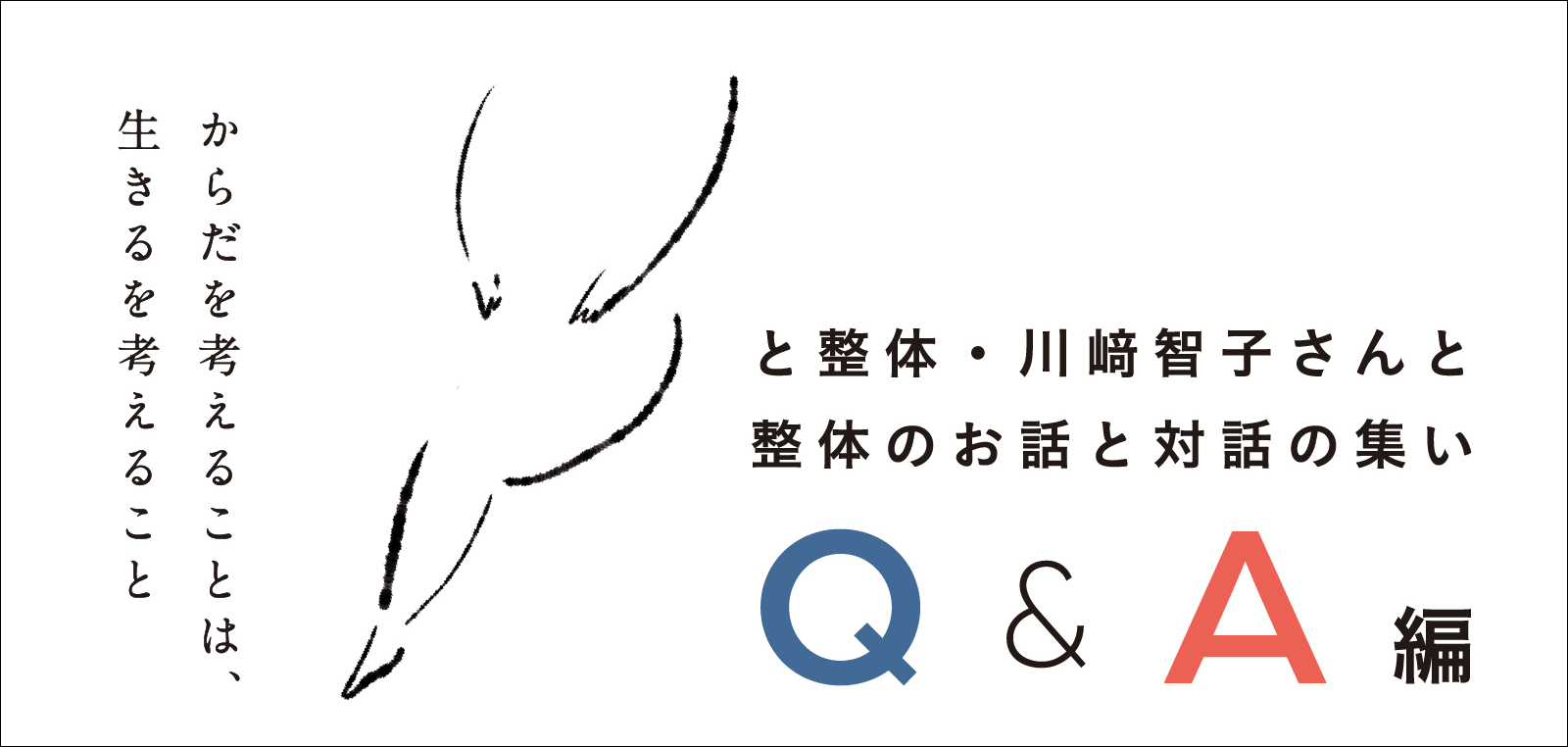福岡・朝倉
松末小、最後の卒業式
〜後編 2〜
144年の歴史の最後の年、松末小を見舞った豪雨災害。「最後の卒業式を松末小で」を合言葉に、地域、そして県外から集まった大人たちが力を合わせます。
災害が起こったとき、当事者でない人は心を痛め、自問します。何かできることはないかと。その「何か」とは何か、また被災者自身はどのように自らを悼み、前へ進もうとするのか。「そのひとつの例として、見てくれたら嬉しい」とゆにこさんは言います。
写真 戸倉江里
取材・文 松本あかね
●
栄えて永遠なれ
木と朝
わたしたちは
いっぽんの木
大地に立つ
いっぽんの木
はるか太古に
ひとつの星から
生まれた光は
末々までゆきわたり
小さな学び舎を
優しくつつむ
そこでは
うれしいこともあった
つらいこともあった
かなしいこともあった
たのしいこともあった
こころの内深くから
湧きいづる
すべての涙は
笑顔という名の
海に達する
そして
小さな学びとたちよ
ひとりひとりは小さいけれど
わたしたちは大きな大きな
いっぽんの木であることを
忘れてはならない
新しい朝の光を
受けとめるために

食事がひと段落した頃、詩の朗読が始まった。
「松末小学校と聞いたときに、なんて素敵な名前なんだろう、と思いました」
最初にshunshunさんはこう言った。「縁起が良いとされる『松』、それから“末広がり”の『末』で永遠に続くものという意味があるのです」と。
そう言われて「え」、皆びっくりした。無理もない。学校はもうなくなると、ずっとそう思ってきたから。
今回shunshunさんがお願いされたのは“ネームドローイング”。漢字の起源である象形文字をさらに遡り、文字となる以前、まだ絵だった時代にまで戻ってみるという試みだ。
「『松末小学校』のドローイングを描いたら、まるで一本の木のように見えてきたんです。皆で支え合う、子どもたちひとりひとりと先生たちとでできあがった木のように」

ネームドローイングでは、線と線が響き合うことで文字の持つ意味を超えて新しいイメージが生まれる。冒頭の詩は「松末小学校」の文字を線画に起こしたときに浮かんだイメージを、言葉に移し替えしたものだという。それは何か、始まりの詩のようで、会場全体の空気がにわかに変わったようだった。
●
心に沁みる音楽

会の間、この日のために用意された真新しいグランドピアノを弾くのは、haruka nakamuraさん。共に柔らかなサックスの音色を響かせる内田輝さん。空気に寄り添うように即興で生み出されるメロディが静かに染みていく。
映像:澤村和博(映像クリエーター)
♪もう帰ってこい
まったく君って人はどこまでやさしい人なのかしら
私のもとにはやく戻って
いっしょにご飯を食べましょう
揚げ足の取り合いとか
格好のつけ合いとか
もううんざり
ほんとうんざり
しているんでしょう
あなたはもっと小さな人間だったのよ
器じゃなかったの
でもそれがなんだっていうの
……
斎藤キャメルの初ソロアルバム「海のまえ、森のなか」に収録
『喜びは食卓に 悲しみはトイレに』
齋藤キャメル(WATER WATER CAMEL)
斎藤キャメルさんのシルキーな歌声が流れる。ゆにこさん曰く「私の言いたいことは基本的にこの歌詞の中に入ってるから」。ちっちゃな子どもたちに聴いてもらうにはどうなんでしょう、とキャメルさんはドキドキしていたけれど、ほら、向こうの席で一心に聞き入っている人がいる。この一年を乗り越えて、生徒たちを送り出す大仕事を成し遂げた今、全身で聴き入っている先生。その姿は魂に栄養を注ぎ込まれ、彩度が増していくかのよう。

●
これで終わりではなく
会も佳境の頃、さんざめく会場を見守っていたのは、隣町うきはにある『MINOU BOOKS&CAFE』の石井さんだ。ゆにこさんのサポート役としてさまざまな相談にのってきた。感無量ですか? と問うと「はい、もうやりきったなって」。でも、と言葉を継ぐ。
「これで終わりかといえばそうではないので。僕らからすると、明日も会うし一週間後も会うし、みたいな距離感だから。災害のあった場所からどのくらいの距離かということは、気持ちの上ですごく違います。だから関わることは自然だったし、長くなるなとも思いました。これからも日常の中で自分たちにできることをやっていくしかないです」
淡々とした表情に隣人としての真摯さを見る思いがした。

皆それぞれに生活があり、生活がもたらすさまざまな事情の中で暮らしている。その場所で私たちはそれなりに必死だ。けれど、もし同じ国に生活そのものを根幹から覆された人がいると聞けば、いてもたってもいられない気持ちに襲われる。」

多くの人は、何かできればと祈るような気持ちを抱えながら、自分に何ができるのか、また何が必要とされているのかわからないまま時が過ぎる。そして何年か経ったとき、再びどこかで災害が起き、新たな被災地と被災者が生まれる。そのことが繰り返されるうち、いつしか国土が荒れ、人が傷つくことを悼む心が麻痺していくような感覚をどこかで感じていないだろうか。
「被災地について考えるきっかけになるのは、実際に足を踏み入れてその方を近くに感じること」とゆにこさんは言った。
ゆにこさんの場合、きっかけは豪雨のほんの数時間前の「お店探検」だった。支援にはいろんな形があっていい。ゆにこさんが目指したのは、サプライズでもエンターテイメントでもなく、日常にそっとある楽しみの温もりを伝えること。心がほっと休まる波止場のような場所を作ること。
今回集まったのは、そういうことの力を信じている人たち。
「今日、ここに集まった大人のことはずっと信じられる気がする」
キャメルさんは言った。
大人たちは自分にできること、と言いながら、自分の信じるものを差し出したのだと思う。その記憶が子どもたちの中で形を結び、何年も先まで支え続けてくれることを信じて。

●
エピローグ
くずかけがつなぐ再会の時
食事会のためにゆにこさんが作ったのは3品の料理。総監督として寝る間もない中、前日の夜遅くと当日の朝早く、厨房に駆け込んで仕上げた『くずかけ』はその一つ。根菜、お豆腐、コンニャクがたっぷり入った具沢山の汁物で、この辺りで人が集まるときに出される郷土料理だ。
現在、ゆにこさんは市内のアパートで暮らす。松末地区の多くの人たちが同様で、別々に暮らす家族もあると聞く。総勢200人が集まる卒業式は保護者、地域の人たちにとって再会の時でもあったのだ。
「華やかな料理はお任せして、私はくずかけを作ります」と話していたゆにこさん。その横顔に大人になった“松末っ子”の姿が重なったように見えたのは、たぶん気のせいじゃない。

福岡・朝倉 松末小、最後の卒業式